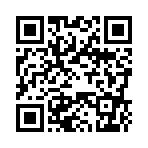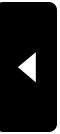2023年06月19日
溶接機 EENOUR MIG120L(100V機) 試用
長年使ってきたM社の半自動溶接機が、購入当初から何かと使い難くサポートもガッカリで、気が乗らない工具の一つになっていました。
それでも200Vの半自動機、パワーがあるので大抵のニーズには応えてくれるので…
使い難さや億劫になるシーンで補助的に使えればと購入したのがHAIGE社のHG-MMA-140D、今からちょうど4年前のことです。
MMAの名の通り、溶接棒を挟んで使うタイプ。
100V/200V兼用機なので200Vで運用し、手軽な一台として使ってきました。
使い難さから億劫になるシーンで補助的に使えればと購入したのがHAIGE社のHG-MMA-140D、今からちょうど4年前のことです。
MMAの名の通り、溶接棒を挟んで使うタイプ。
100V/200V兼用機なので200Vで運用し、手軽な一台として使ってきました。
やがて携行し現場で使えるバッテリーウェルダーの老朽化もあり、100Vで運用できる溶接機も欲しいなと思っていた時、タイミング良くEENOUR社からMIG120Lというモデルが販売されるというメルマガが届きました。


HAIGE社製品と比べると2/3程度の体積です。
溶接棒を使うMMA方式に加え、ノンガスMIG方式で半自動溶接も出来るモデルです。

コンパクトなボディーに格納されたワイヤー
M社のワイヤーは油断すると大暴れし、時には巻き直さなければならないことも有り、それだけで憂鬱だったのですが、装着は実にスムースです。

空転してしまうことが多く、無理やり締めこんでどうにかなっていた送り部分もストレスゼロです。
ワイヤーは0.8mmと1.0mmが使えますが、パーツを表裏入れ替えるとそれそれに対応し、確実に送り出してくれます。
M社のワイヤーはもっと太かったっけ?
なんて思い実測してみましたが0.8mm、単に硬くてコシがあるだけだったようです。
MMA方式と比べると配線はやや多めです。
取説がちょと解りにくかったのですが、全部繋げた画像を見ればさほどでもありません。

早速試用してみました。
25mmの角パイプ、厚さ1.6mmのいわゆる薄物溶接です。
従来タイプの溶接機では、溶接しているのか穴を塞いでいるのか解らなくなるような事も多々あったのですが、そんな心配も無用の快適さ。インバータの威力恐るべし!
100Vということであまり期待していなかったのですが、試した2.3mmの角パイプや3.0mmのアングル溶接程度ならば、しっかり溶け込んでいるのでバッチリ実用できます。
ビードも綺麗に出ますし、ざっと削っただけですが、実用品ならばパテ埋めや手直しの必要も無い仕上り。
購入して一発目でこの仕上りでしたら文句なしです。
長年懸案だったけれど億劫で手が付かなかったラックの製作をしようかな?
心配なのは、あまりにも快適過ぎて、定格使用率40%(4分使って6分休ませる)というサイクルを守れるかどうか。キッチンタイマーを準備しておいた方が良さそうです。
それでも200Vの半自動機、パワーがあるので大抵のニーズには応えてくれるので…
使い難さや億劫になるシーンで補助的に使えればと購入したのがHAIGE社のHG-MMA-140D、今からちょうど4年前のことです。
MMAの名の通り、溶接棒を挟んで使うタイプ。
100V/200V兼用機なので200Vで運用し、手軽な一台として使ってきました。
使い難さから億劫になるシーンで補助的に使えればと購入したのがHAIGE社のHG-MMA-140D、今からちょうど4年前のことです。
MMAの名の通り、溶接棒を挟んで使うタイプ。
100V/200V兼用機なので200Vで運用し、手軽な一台として使ってきました。
やがて携行し現場で使えるバッテリーウェルダーの老朽化もあり、100Vで運用できる溶接機も欲しいなと思っていた時、タイミング良くEENOUR社からMIG120Lというモデルが販売されるというメルマガが届きました。
HAIGE社製品と比べると2/3程度の体積です。
溶接棒を使うMMA方式に加え、ノンガスMIG方式で半自動溶接も出来るモデルです。
コンパクトなボディーに格納されたワイヤー
M社のワイヤーは油断すると大暴れし、時には巻き直さなければならないことも有り、それだけで憂鬱だったのですが、装着は実にスムースです。
空転してしまうことが多く、無理やり締めこんでどうにかなっていた送り部分もストレスゼロです。
ワイヤーは0.8mmと1.0mmが使えますが、パーツを表裏入れ替えるとそれそれに対応し、確実に送り出してくれます。
M社のワイヤーはもっと太かったっけ?
なんて思い実測してみましたが0.8mm、単に硬くてコシがあるだけだったようです。
MMA方式と比べると配線はやや多めです。
取説がちょと解りにくかったのですが、全部繋げた画像を見ればさほどでもありません。
早速試用してみました。
25mmの角パイプ、厚さ1.6mmのいわゆる薄物溶接です。
従来タイプの溶接機では、溶接しているのか穴を塞いでいるのか解らなくなるような事も多々あったのですが、そんな心配も無用の快適さ。インバータの威力恐るべし!
100Vということであまり期待していなかったのですが、試した2.3mmの角パイプや3.0mmのアングル溶接程度ならば、しっかり溶け込んでいるのでバッチリ実用できます。
ビードも綺麗に出ますし、ざっと削っただけですが、実用品ならばパテ埋めや手直しの必要も無い仕上り。
購入して一発目でこの仕上りでしたら文句なしです。
長年懸案だったけれど億劫で手が付かなかったラックの製作をしようかな?
心配なのは、あまりにも快適過ぎて、定格使用率40%(4分使って6分休ませる)というサイクルを守れるかどうか。キッチンタイマーを準備しておいた方が良さそうです。
Posted by 電脳職人 at 19:00│Comments(0)
│道具