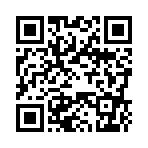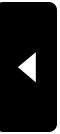2017年03月02日
速報! Uuni3 Wood-Fired OVEN 新発売
NETSHOPのリニューアルに伴い、Uuni3のリンクがこちらに変わりました!
皆さんこんばんは
Uuni 2そしてUuni 2Sと進化を遂げたペレットオーブンの最新モデル

UUNI 3 がメーカーホームページに掲載されました。
2017.03.01世界同時発売というサプライズ
情報が入って来なかったので、私も全貌を初めて知りました。
日本は少々遅れていますが、間もなく入荷する見込みです。

顔はほとんど変わりません。

後部が絞られ、凸凹がある場所でも安定するよう、脚が3本になったのが外観上の大きな特徴です。
カロリーはUuni 2Sと変わらず、500℃という石窯並の燃焼温度。
点火から実用温度へ達するまで10分間。
など、基本スペックは同じですが、後部が絞られたことや断熱性能の向上により、ピザの焼き上げ時間は90秒から60秒に短縮されています。
皆さんこんばんは
Uuni 2そしてUuni 2Sと進化を遂げたペレットオーブンの最新モデル

UUNI 3 がメーカーホームページに掲載されました。
2017.03.01世界同時発売というサプライズ
情報が入って来なかったので、私も全貌を初めて知りました。
日本は少々遅れていますが、間もなく入荷する見込みです。

顔はほとんど変わりません。

後部が絞られ、凸凹がある場所でも安定するよう、脚が3本になったのが外観上の大きな特徴です。
カロリーはUuni 2Sと変わらず、500℃という石窯並の燃焼温度。
点火から実用温度へ達するまで10分間。
など、基本スペックは同じですが、後部が絞られたことや断熱性能の向上により、ピザの焼き上げ時間は90秒から60秒に短縮されています。
細部を説明する前に、おことわりしておかなければなりませんが、現況でのネットショップやこのブログに掲載されている内容は、オフィシャルサイトの内容を翻訳し、Youtubeに掲載されている動画と今までの私どもの経験に基づいたものです。
かねてから口にしていますが、Uuniは精力的に商品開発をされていますし、国内正規代理店からの正式なアナウンスに基づく内容でもありませんので、大筋において間違いは無いと思いますが、細部につきましては仕様変更が為されていたり解釈が違う部分もありますのでご容赦ください。
それでは、主な変更点からいきます。

チムニー(煙突)が、パッチン金具に変更されました。
工具を使わなくて済むよう、電脳工房で独自に蝶ボルトを添付してきましたが、これでもっと楽になります。

隔壁が復活しました。
ほーら、やっぱり必要でしょ?っと感じです。
Uuni 2Sをお使いの皆さん、ぜひご検討ください。
※在庫が無くなり次第受注生産に切り替えます。
蓄熱板と本体の隙間に挟むので、脱着も容易です。
かなり小型ですが、正直言いますと、ピザが60秒で焼けることより、Uuni 2Sの90秒(隔壁を装着すると120秒くらい)、Uuni 2の120秒になっても良いので、大慌てしなくても焦げずに美味しく焼けて欲しいと思っています。また、耐熱容器は炎が直接当たると割れてしまいます。
実際に使ってみて、状況によってはラージサイズ(Uuni 2サイズ)の製作を考えます。
実は、Uuni 2S用の隔壁を試作した際、このような形状の物も作ったのですが、ピザを投入した時に勢い余り、押して倒れてしまうことが有りました。
UUNI 3ではこの辺りの形状が大幅に変更されていますので、押し倒してしまうことは無いのかもしれませんが、そういう症状を呈するようでしたら、やはりネジ止めする物を考えると思います。
ただし、そこまで拘る方は少ないと思いますので、希望される方を募って一回こっきりで製作することになると思います。
状況によってはと書きましたが、この辺りはホッパーのところで再度説明します。

庫内の形状やサイズはほとんど変わらず、蓄熱板も互換性があります。

バーナー部は大きく変わりました。
私は点火・消火時以外、抜き差しする事はありませんが、長時間運用する際は、灰の処理などし易いかもしれませんね。

今までのモデルは、円筒の高さで燃焼部に落ちるペレット量を変え、温度を調整していたのですが、UUNI3ではプレートの傾斜を変えることによりスリットの広さを変え、ペレット量の調整をします。
三段階だったものが無段階になり、きめ細かい調整ができるようになったようです。
隔壁のところで状況によってはと書きましたが、隔壁が小さくなっても、こうして温度調整がし易くなったことで、十分コントロールできるのかもしれません。
高火力にして大きな隔壁で拡散した場合と、火力を落として小さい隔壁で拡散した場合に、大して差異が無ければラージサイズの隔壁など製作する必要もありません。先ずは試用してこの辺りを重点的にチェックしてみたいと思います。

ところで、メディアの調整は六角レンチでネジを回すようです。
個人的には、これはちょっと嫌ですねぇ。
バーナー直上ですのでどの程度温度が上がるのか、実測してみないと何とも言えませんが、何かしらツマミを取り付けて工具無しで回せるようにしたいと思います。極端な話し、六角レンチで回すくらいなら、手袋をしても蝶ボルトを回した方がマシに思えます。
ここは宿題ということにさせていただきますが、これはというアイデアがありましたら、お寄せ頂けると嬉しいです。

ホッパーがこのような形状になったので、スコップはチムニーのキャップと兼用になりました。
スコップが邪魔でホッパーの中程までしかペレットが入れられなかったので、この仕様変更は大歓迎です。
形状的にも零れにくそうですね。
先ずは使ってみたいです。
もう一つ気になる点ですが、ホッパーが少し小さいのではないかという点です。
Uuni 2の頃から、これで暖を取ることはできないかという質問を何度かいただいており、先日、スクリーンタープへのフラッシングキットを装着も終えましたので、確認してみようと思っているのですが、上手い具合に使えるようでしたら、あまり手間を掛けずに長時間運用したくなるのが目に見えています。
そうでなくても、生地から手作りをしたり、グルキャンで人数が多かったり、子どもたちのトッピングの面倒を見たりしていると、うっかり切らしてしまうなんてことがあります。
ここも物足りなさを感じたら、ラージホッパーを製作します。
とりあえず、前2モデルを使い倒し、とても重宝していますので、UUNI 3への期待も大きいです。
相変わらず、かなりひいき目に補助パーツ等を考え、今回は点火方法から基本的な使い方をまとめたマニュアルも独自に作り、提供しようと思っています。
お解りにならない点などありましたら、どうぞご遠慮なくお尋ねください。
初めてお使いになる方も、精一杯バックアップさせていただきますので、お買い求めもぜひ電脳工房で!
かねてから口にしていますが、Uuniは精力的に商品開発をされていますし、国内正規代理店からの正式なアナウンスに基づく内容でもありませんので、大筋において間違いは無いと思いますが、細部につきましては仕様変更が為されていたり解釈が違う部分もありますのでご容赦ください。
それでは、主な変更点からいきます。

チムニー(煙突)が、パッチン金具に変更されました。
工具を使わなくて済むよう、電脳工房で独自に蝶ボルトを添付してきましたが、これでもっと楽になります。

隔壁が復活しました。
ほーら、やっぱり必要でしょ?っと感じです。
Uuni 2Sをお使いの皆さん、ぜひご検討ください。
※在庫が無くなり次第受注生産に切り替えます。
蓄熱板と本体の隙間に挟むので、脱着も容易です。
かなり小型ですが、正直言いますと、ピザが60秒で焼けることより、Uuni 2Sの90秒(隔壁を装着すると120秒くらい)、Uuni 2の120秒になっても良いので、大慌てしなくても焦げずに美味しく焼けて欲しいと思っています。また、耐熱容器は炎が直接当たると割れてしまいます。
実際に使ってみて、状況によってはラージサイズ(Uuni 2サイズ)の製作を考えます。
実は、Uuni 2S用の隔壁を試作した際、このような形状の物も作ったのですが、ピザを投入した時に勢い余り、押して倒れてしまうことが有りました。
UUNI 3ではこの辺りの形状が大幅に変更されていますので、押し倒してしまうことは無いのかもしれませんが、そういう症状を呈するようでしたら、やはりネジ止めする物を考えると思います。
ただし、そこまで拘る方は少ないと思いますので、希望される方を募って一回こっきりで製作することになると思います。
状況によってはと書きましたが、この辺りはホッパーのところで再度説明します。

庫内の形状やサイズはほとんど変わらず、蓄熱板も互換性があります。

バーナー部は大きく変わりました。
私は点火・消火時以外、抜き差しする事はありませんが、長時間運用する際は、灰の処理などし易いかもしれませんね。

今までのモデルは、円筒の高さで燃焼部に落ちるペレット量を変え、温度を調整していたのですが、UUNI3ではプレートの傾斜を変えることによりスリットの広さを変え、ペレット量の調整をします。
三段階だったものが無段階になり、きめ細かい調整ができるようになったようです。
隔壁のところで状況によってはと書きましたが、隔壁が小さくなっても、こうして温度調整がし易くなったことで、十分コントロールできるのかもしれません。
高火力にして大きな隔壁で拡散した場合と、火力を落として小さい隔壁で拡散した場合に、大して差異が無ければラージサイズの隔壁など製作する必要もありません。先ずは試用してこの辺りを重点的にチェックしてみたいと思います。

ところで、メディアの調整は六角レンチでネジを回すようです。
個人的には、これはちょっと嫌ですねぇ。
バーナー直上ですのでどの程度温度が上がるのか、実測してみないと何とも言えませんが、何かしらツマミを取り付けて工具無しで回せるようにしたいと思います。極端な話し、六角レンチで回すくらいなら、手袋をしても蝶ボルトを回した方がマシに思えます。
ここは宿題ということにさせていただきますが、これはというアイデアがありましたら、お寄せ頂けると嬉しいです。

ホッパーがこのような形状になったので、スコップはチムニーのキャップと兼用になりました。
スコップが邪魔でホッパーの中程までしかペレットが入れられなかったので、この仕様変更は大歓迎です。
形状的にも零れにくそうですね。
先ずは使ってみたいです。
もう一つ気になる点ですが、ホッパーが少し小さいのではないかという点です。
Uuni 2の頃から、これで暖を取ることはできないかという質問を何度かいただいており、先日、スクリーンタープへのフラッシングキットを装着も終えましたので、確認してみようと思っているのですが、上手い具合に使えるようでしたら、あまり手間を掛けずに長時間運用したくなるのが目に見えています。
そうでなくても、生地から手作りをしたり、グルキャンで人数が多かったり、子どもたちのトッピングの面倒を見たりしていると、うっかり切らしてしまうなんてことがあります。
ここも物足りなさを感じたら、ラージホッパーを製作します。
とりあえず、前2モデルを使い倒し、とても重宝していますので、UUNI 3への期待も大きいです。
相変わらず、かなりひいき目に補助パーツ等を考え、今回は点火方法から基本的な使い方をまとめたマニュアルも独自に作り、提供しようと思っています。
お解りにならない点などありましたら、どうぞご遠慮なくお尋ねください。
初めてお使いになる方も、精一杯バックアップさせていただきますので、お買い求めもぜひ電脳工房で!
この記事へのコメント
いつも楽しく読ませていただいております。
uuni2sを使用しておりますが、やはり隔壁の
必要性を感じています。今回uuni3にて復活
したとのこと、ため息まじりで読みました。
電脳工房で販売なさっている隔壁は、ネジ止め
のものと理解しております。ネジ止めでない
「蓄熱版に挟み込む」スタイルの隔壁の販売予定は
おありでしょうか。
お忙しいとは存じますが、よろしくお願い致します。
uuni2sを使用しておりますが、やはり隔壁の
必要性を感じています。今回uuni3にて復活
したとのこと、ため息まじりで読みました。
電脳工房で販売なさっている隔壁は、ネジ止め
のものと理解しております。ネジ止めでない
「蓄熱版に挟み込む」スタイルの隔壁の販売予定は
おありでしょうか。
お忙しいとは存じますが、よろしくお願い致します。
Posted by ミラノ未渡航 at 2017年04月04日 17:05
>ミラノ未渡航さん
コメント&いつもブログをご覧くださり、有り難うございます。
Uuni3を使用して、やはりラージ隔壁が必要だと感じており、穴を開けなくて良い方法でのリリースを検討しています。形状的には2/2Sも共通でお使いいただけると思います。
今までのサイズでは左右が僅かに納まらず、サイズダウンし、実際に使ってみてということになりますので、GWを越えてしまうのではないかと思います。
目下提供できますのは、試作して弊社で2度ほど使用した物を、中古として販売をと考えている物だけで、暫くお待たせしてしまうことになると思いますが、どうぞよろしくお願いします。
コメント&いつもブログをご覧くださり、有り難うございます。
Uuni3を使用して、やはりラージ隔壁が必要だと感じており、穴を開けなくて良い方法でのリリースを検討しています。形状的には2/2Sも共通でお使いいただけると思います。
今までのサイズでは左右が僅かに納まらず、サイズダウンし、実際に使ってみてということになりますので、GWを越えてしまうのではないかと思います。
目下提供できますのは、試作して弊社で2度ほど使用した物を、中古として販売をと考えている物だけで、暫くお待たせしてしまうことになると思いますが、どうぞよろしくお願いします。
Posted by 電脳職人 at 2017年04月04日 19:02
at 2017年04月04日 19:02
 at 2017年04月04日 19:02
at 2017年04月04日 19:02早速のお返事、ありがとうございました。
ラージ隔壁(ネジ止めしないバージョン)の
リリースを首を長くして待っております。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
ラージ隔壁(ネジ止めしないバージョン)の
リリースを首を長くして待っております。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
Posted by ミラノ未渡航 at 2017年04月18日 08:47
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。