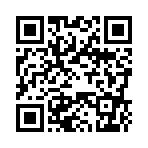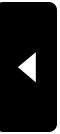2014年08月26日
能登・珠洲の海水から塩作り

能登の先端、珠洲の塩田近くにある海岸から汲んできた海水
塩を作る気満々だったのですが、製塩工程の説明を受けたら、すっかり意気消沈してしまいました。
しかし、よくよく考えてみると、塩田では砂に海水をぶちまけ、乾燥効率を良くするため庭園のように砂に筋を付け、乾いた頃を見計らい濃度が上がった砂混じりの塩を回収し、煮てアクや不純物を取り除くという工程があります。
不純物を取り除く工程が二回と聞き、何とも面倒だなと思っていたのですが、最初から煮詰めて作るのでだいぶ工程は簡略されます。
ずっとやってみたかった事なので、いつかきっとまたやりたくなることでしょう。
そんな調子で、アウトドア倶楽部 nature(ネイチャー)では、メンバーの企画で川原でドラム缶風呂をやってみたり、切り出してきた竹でご飯を炊き、食器を作るなんてこともやってきました。
「何時かやってみたい」は、やってみると思いの外難しくなく、そして楽しいものです。
折角汲んできたので、面倒になる前にやってみましょう。

先ずは濾過。
海水を汲むとき、波打ち際だったので、砂が結構入ってきたのですが、すぐに沈むので上澄みだけを入れてきました。
こうして濾過しても、本当に細かい不純物が少し取り除かれる程度、とても綺麗な海水でした。
それでも、しばらく濾過していると、段々水の落ち方が緩慢になってきました。目に見えないくらい小さい不純物があるのでしょうね。

今回は長丁場になることが予想されるので、燃費と火力のバランスが良い、ファロス・ストーブNo.2を使うことにしました。
大きな鍋を乗せても余裕のサイズ、グルキャンなどでは重宝するのですが、マナスル製品に切り替えたため、修理時の代替機(貸出機)を兼ねたこれも出番が無くなります。ネットショップのアウトレットコーナーに並べようかと思っていた矢先、活躍の場ができました。
ケロシンストーブは、使い始めにプレヒートの手間がありますが、長時間煮込むような調理では、その手間よりも燃料費の安さが大きなメリットになります。
ケロシン(灯油)が燃料と聞くと、何だか物足りないのではないかと思う方もいらっしゃると思いますが、気化された灯油はファンヒーターと同様結構な火力で燃焼し、ホワイトガソリンタイプと比べても遜色ないくらいです。

さて、作業開始!17:00のスタートで果たして今日中に塩が出来るのか!?

3時間経過した20:00、何やらふわふわした白い物が漂ってきました。撹拌しても消えることはありませんし、サラサラ感があるので明らかに塩の結晶とは異なります。

時間の経過とともに、どんどん増えていきました。

20:45 当初の量から1/10ほどまで煮詰まり、白い物質の増加も一段落した感じです。
この白い物質は、硫酸カルシウム(CaSO4)、一般的に石膏と呼ばれる物だそうです。
漢方では解熱作用や止渇作用、美容では石膏パック、医療ではギブスに使われる物ですが、こんな風にして抽出できるのは何だか不思議な感じがします。

およそ4~4.5Lの海水から、こんなに沢山抽出されました。

コーヒーフィルターをつかって濾過し、念入りに取り除きます。

ここからは、鍋を一回り小さくして煮詰めていきます。これは正解でした。

沸騰し、しばらくの間は無色透明のままだったので、硫酸カルシウムを除去するタイミングとしてはバッチリだったのでしょう。この辺りの見極めは思っていたよりも簡単で解りやすかったです。
画像は21:10の状態、濾過工程で10分ほど時間差がありますので作業再開から15分程度、一気に塩が出来る感が高まってきました。
もしかして無事塩が出来上がる?という期待に、とってもワクワクします。

21:35 どんどん粘度が上がっていきます。
塩の大きい粒を作りたいのであれば、そっとしておいた方が良さそうですが、大きな泡が弾けると熱いどろどろの液体が飛んでくるので、こまめにかき回しました。こうするとだいぶ緩和されます。

ここからの見極めが肝心… という時に珍客登場。
最近はコクワガタすら見掛けることが少なくなったのですが、ノコギリクワガタがどこからともなく近付いてきました。
雨降りで寒かったのでストーブの暖に吸い寄せられたのでしょうか、熱いどろどろが掛かっては可哀想と手を伸ばしたら、とても激しく威嚇してきました。

21:50 あっという間に塩らしくなっていきました。
この辺りの変化は本当に一気という感じですから目が離せません。
塩田の売店には、結構白い塩と、やや赤みがかった塩が売られており、同じ製法なのだけれど製造したロットによって色が異なるという説明を受けました。
あとで考えてみると、苦汁が綺麗な琥珀色をしていたので、その混じり具合なのではないかと思えます。
実際こうやって作業してみると、あまり煮詰めすぎると苦汁を含んだ水分も少なくなり、濾過しても塩の方に残留することに。かといって煮詰め方が足りないと結晶になり切らなかった塩分が苦汁の方へと行き、幾分しょっぱい苦汁が出来ることになります。
その辺りでベストなタイミングを
ここが塩作りのキモだと思います。

程良く水分を残したまま濾過します。

下に落ちた水分、これが天然の苦汁というわけです。
塩の湿気は苦汁混じりなので、苦みを減らすため入念に濾過、塩田では一ヶ月掛かりで分離をしているそうです。
売り物ではないですし、試用してみても違和感が無かったので、程々で良いと思うのですが、フォークで耕すとちろちろ出て来るので、こまめにかき混ぜてみたり、ペーパーフィルターを交換して吸わせたりしました。
一晩経ったら結構サラサラになっていたので、キッチンペーパーを重ね、その上に塩を広げました。
乾燥させても良いのかもしれませんが、しっかり吸い出すことで苦汁も除かれ、キレが良い塩になるかなと…
昨晩、鶏軟骨の味付けに一つまみ入れてみましたが、贔屓目にならぬよう辛口を心掛けても美味い塩が出来上がったいました。

すっかり気をよくして今日は寸胴で作ります!(笑)
こんな事が大好き!なアウトドア倶楽部 nature は、mixiでの交流を中心にしたグループです。
顔を見渡せる人数で、皆が安心し、相互に信頼関係をもち、家族的なお付き合いができるよう、承認制・非公開で運営しています。
来月頭には、天空のキャンプ場で、今回の苦汁を使った豆腐作り。
中旬の連休は南伊豆で海遊び・カヤックツーリング・釣り、そして綺麗な海水を汲んで塩作りをし、珠洲の塩と味比べ。
下旬は標高1,500mのキャンプ場で、眼下の湖畔と空に広がる星空の間に身を置き焚き火を楽しむ。
といった感じで、多いときには30余名、少ないときには3~4名で、「印象に残るキャンプ」をテーマに楽しんでいます。
http://mixi.jp/view_community.pl?id=6046909
楽しいこと大好き!な皆さまのご参加をお待ちしています。
Posted by 電脳職人 at 11:09│Comments(0)
│雑記帳
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。