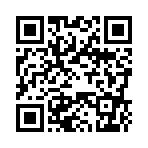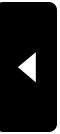2014年02月10日
Ozpig 煙突横出し用パーツ製作
Ozpigがグレードアップして新登場!
最新モデル(2019.11発売) Ozpig FIRESIDE EDITIONは こちら です。

全国各地大雪になった週末、信州も例に漏れず久し振りの本降り、県下要所が30cmを越えるなか、当地松本は一際多い49cm、楽しみにしていたPICA富士西湖でのイベントも、雪かきのため諦めざるをえませんでした。
幸い四駆のハイエースはものともせず突き進んでくれるので、閉じこめられるということは無かったのですが、何処へ行っても危なっかしい車や、ノロノロ運転の車に翻弄され、時間のロスが大きいので諦めて早々に帰着、ただ雪かきをして週末を過ごすのも癪に障るので、懸案になっていたパーツを製作することにしました。


コンパネで三角柱を倒した形状で製作する方が多いのですが、折角愛嬌があるOzpigですから、遮熱を兼ねて見栄えがするよう、アルミ複合板に、DI-NOC木目調フィルムと、サンゲツのレンガ調フィルムを使ってみました。

背面がご覧の通り、一般的な形状ですが、遮熱板が有る分だけ熱のロスも少ないと思いますし、隙間風の緩和にもなるかな?と思っています。
テントやスクリーンタープのファスナーを途中まで開け、この木目部分を差し込み、布ガムテープ等を使って生地を密着させます。
バネでパチンと紙を挟むバインダーで使われているような金具を何個か取り付け、生地を挟むだけで済むようにしようかとも考えていたのですが、木目部分はアルミ成型フレーム+ABS樹脂コーナーを使っていてかなり頑丈、脚を準備すればテープルとして充分使える(共用できる)ので、気持ちはそちらの方に傾いています。

最下部の穴は吸気用で、直近に新鮮な空気を取り入れられるようにしてみます。Ozpigの直下を通すことで、少しは空気が暖められるかもしれない、そして、少なくとも(吸気による)隙間風は防げるだろうと期待しています。
排気ファンの設置は、実用してみてから考えることにしました。

木目の土台部分と遮熱パネルは、フレームにブラインド・ナットを埋め込んでいるので、4箇所の蝶ネジで脱着でき、更に半分にすることができます。

背面パネル(遮熱パネル)は、土台部分に収納することができます。
取手とパッチン金具でも付けてアタッシュケースのように持ち歩きできるようにしようと考えています。
最新モデル(2019.11発売) Ozpig FIRESIDE EDITIONは こちら です。

全国各地大雪になった週末、信州も例に漏れず久し振りの本降り、県下要所が30cmを越えるなか、当地松本は一際多い49cm、楽しみにしていたPICA富士西湖でのイベントも、雪かきのため諦めざるをえませんでした。
幸い四駆のハイエースはものともせず突き進んでくれるので、閉じこめられるということは無かったのですが、何処へ行っても危なっかしい車や、ノロノロ運転の車に翻弄され、時間のロスが大きいので諦めて早々に帰着、ただ雪かきをして週末を過ごすのも癪に障るので、懸案になっていたパーツを製作することにしました。


コンパネで三角柱を倒した形状で製作する方が多いのですが、折角愛嬌があるOzpigですから、遮熱を兼ねて見栄えがするよう、アルミ複合板に、DI-NOC木目調フィルムと、サンゲツのレンガ調フィルムを使ってみました。

背面がご覧の通り、一般的な形状ですが、遮熱板が有る分だけ熱のロスも少ないと思いますし、隙間風の緩和にもなるかな?と思っています。
テントやスクリーンタープのファスナーを途中まで開け、この木目部分を差し込み、布ガムテープ等を使って生地を密着させます。
バネでパチンと紙を挟むバインダーで使われているような金具を何個か取り付け、生地を挟むだけで済むようにしようかとも考えていたのですが、木目部分はアルミ成型フレーム+ABS樹脂コーナーを使っていてかなり頑丈、脚を準備すればテープルとして充分使える(共用できる)ので、気持ちはそちらの方に傾いています。

最下部の穴は吸気用で、直近に新鮮な空気を取り入れられるようにしてみます。Ozpigの直下を通すことで、少しは空気が暖められるかもしれない、そして、少なくとも(吸気による)隙間風は防げるだろうと期待しています。
排気ファンの設置は、実用してみてから考えることにしました。

木目の土台部分と遮熱パネルは、フレームにブラインド・ナットを埋め込んでいるので、4箇所の蝶ネジで脱着でき、更に半分にすることができます。

背面パネル(遮熱パネル)は、土台部分に収納することができます。
取手とパッチン金具でも付けてアタッシュケースのように持ち歩きできるようにしようと考えています。
Posted by 電脳職人 at 13:00│Comments(0)
│Ozpig(オージーピッグ)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。